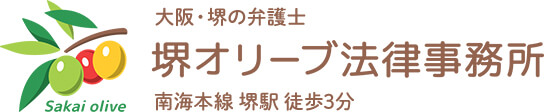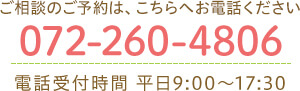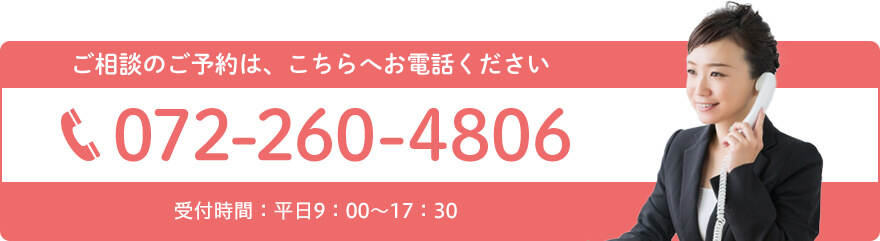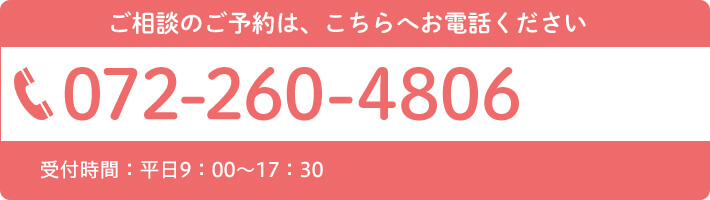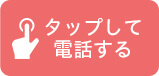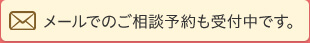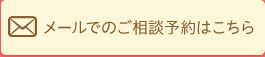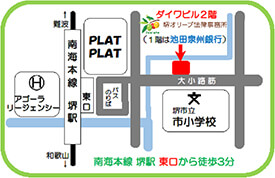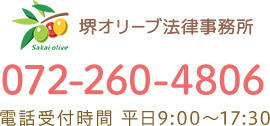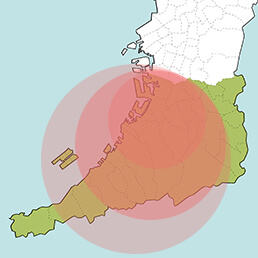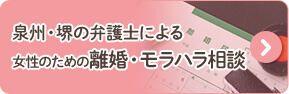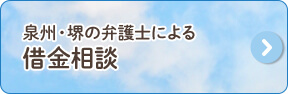相続

遺産分割、遺留分侵害額請求、遺言書作成、寄与分、被相続人の財産の不当流用、遺言書検認、相続放棄申述、包括遺贈放棄申述、遺留分放棄許可審判申立て、相続財産管理人選任審判申立て、特別縁故者など、相続に関する様々な分野を取り扱っています。
Contents
遺産分割
相続が発生したとき、遺族(相続人)の間で揉めることなく遺産分割についての話し合いがまとまればよいのですが、揉めた場合、法的な手続きに入ることになります。
たとえば・・・
・兄弟姉妹間で意見が合わない
・親が生きている間に、一部の兄弟のみが様々な援助を受けており、不公平が発生している
・相手に連絡しても、無視されてしまって、話し合いをすることすらできない
・きょうだいのうち一人だけが、亡くなった親の介護をしてきたのに、不平等だ
などを理由に、遺産分割トラブルは発生しています。
その場合、弁護士が代理人として遺産分割協議をして話がまとまることもあります。
また、弁護士が間に入ることで、自分の希望を叶えるために様々な手段がとれることになりますし、相手の理不尽な主張も斥けられるようになります。
遺留分侵害額請求
亡くなった父が遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書いていた場合でも、次男は、全然相続できなくなるわけではなく、一定の割合の遺産を受け取る権利があります。これを遺留分と言います。
遺留分は、相続トラブルの中でも遺産分割トラブルと同じくらい多いトラブルであり、
・一部の相続人に対してだけ生前贈与が行われている
・一人にだけ相続させるという遺言が出てきた
・そもそも相続があったことを知らなかった
などを理由に、遺留分トラブルは発生しています。
父が亡くなる直前に長男に全財産を生前贈与してしまっていた場合でも、次男には遺留分があります。
この遺留分を請求する権利を行使することを「遺留分減殺請求」と言います。この遺留分減殺請求は、遺贈や贈与があったことを知った時から1年経過すると時効消滅してしまいますので、注意が必要です。
遺留分をめぐって揉めてしまうようなケースは、相続財産が大きいことが多く、不動産の評価額など専門的な知識が無ければ、適切に主張が出来ないということも多いです。あなたが受け取るべき遺産を獲得するためにも、一度弁護士にご相談ください。
相続放棄
親が多額の借金を残して亡くなってしまった場合、そのままですと、借金を相続してしまいます。しかし、相続放棄の手続きをすれば、借金を相続しなくて済みます(その代わり、親の財産も引き継げなくなります)。
この相続放棄の手続きは、まだ被相続人の遺産に何も手を付けてなくて、しかも被相続人死亡後3か月経過していない場合には、比較的簡単に手続きできます。
これに対し、よくあるケースとして、親が亡くなり、何も財産を残していないと思ってほうっておいたら、半年ぐらいしてから、多額の借金が判明した、というケースがあります。この場合、もう3か月経過してしまっているので、相続放棄ができないと思い、諦めてしまう方がいますが、親に借金があったことを知ってから3か月以内なら、相続放棄ができます。ただ、この場合、裁判所への相続放棄申述の手続きが少し工夫が必要になりますので、弁護士に相談することをお勧めします。
遺言書の作成
自分が死亡した後、遺族の間で揉めることがないように、遺言書を作ることができます。
ただ、「常識」だけで遺言書を書くと、思わぬ落とし穴がたくさん潜んでいます。良かれと思って書いた遺言書が、残念ながら、自分の死後、却って遺族の紛争のタネになってしまうことも、実は多く見られます。
遺言書については、ほんのちょっとした言葉遣いの違いで、大きな違いを生じることがしばしばあります。ほんの一例を挙げますと、「長男に相続させる」という言葉と「長男に遺贈する」という言葉では、法律的な意味が全く異なります。
せっかくの遺言書が却って遺族を揉めさせることのないように、遺言書を作成する場合は、ぜひとも弁護士に相談することをお勧めします。